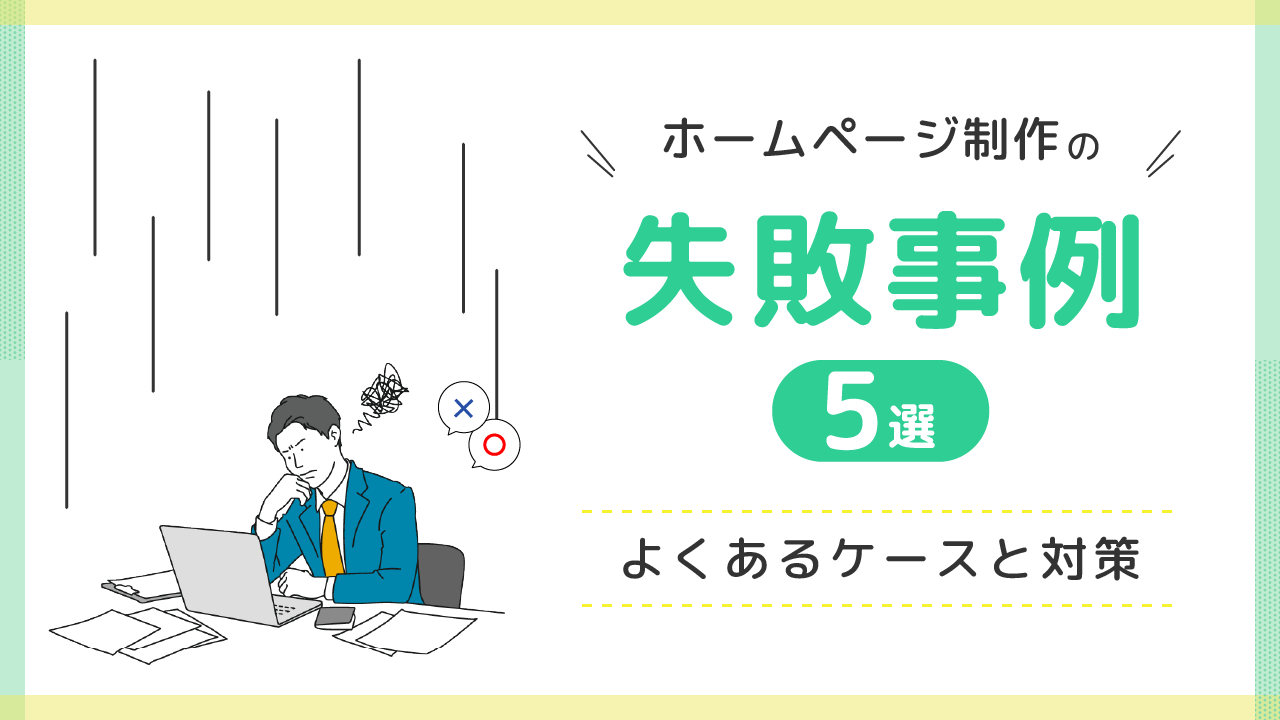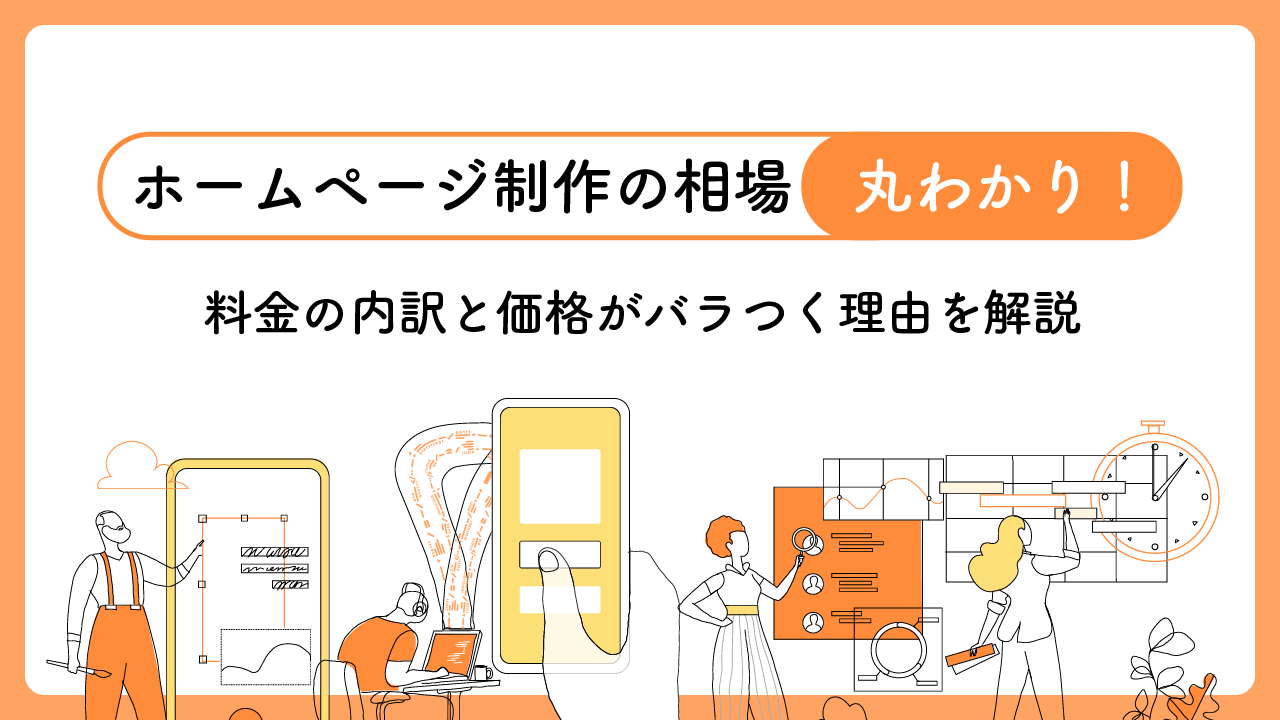目次
はじめに|この記事はこんな方におすすめ
こんにちは!株式会社relationのみえこです。
ホームページ制作は、自社の集客力やブランドイメージに直結するとても大切な取り組みです。しかし、費用をかけたにもかかわらず「思っていた仕上がりと違う」「全く集客につながらないサイトになってしまった」といった失敗は決して珍しくありません。
- 複数社に見積もりを依頼したが、金額がバラバラで判断基準がわからない
- 必要な機能を入れたらコストが膨らみ、予算を大きくオーバーしてしまった
- デザインは良いのに、集客やSEO対策が不十分で成果が出ない
こうした失敗は、依頼前の準備不足や制作会社との認識ズレから起こるケースがほとんどです。本記事では、ホームページ制作でよくある失敗事例と、それを防ぐための具体的な方法を解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 初めてのホームページ制作を検討しており、失敗事例から学んでおきたい方
- 複数社の見積もり金額や内容の差に戸惑い、判断基準がほしい方
- 自社に必要な機能やデザイン、SEO対策の優先順位を明確にして依頼したい方
ホームページ制作の相場や詳しい費用の内訳については、こちらの記事をご覧ください!
ホームページ制作の失敗事例5選
ホームページ制作において、実際に企業が経験した事例をもとに、特に多い5つの失敗パターンを紹介します。
それぞれの失敗事例の内容と具体的な対策を解説しますので、これからホームページを作成・リニューアルされる方はぜひ参考にしてください。
※注意:これから紹介する失敗は、業種や規模に関係なくどの企業にも起こり得ます。「うちは大丈夫」と思っていた会社が、数十万〜数百万円規模の損失を出した例もあります。こちらの記事を参考に、ぜひ自社のホームページ制作にお役立てください。
事例1.「安さ重視」で依頼して後悔する
千葉県で清掃業を営むB社は、創業5年を迎え、新たに自社のホームページを立ち上げることを決めました。
「ネットからの集客を増やしたい」という目的はあったものの、初めての制作で相場感が分からず、複数社に見積もりを依頼。結果は、30万円から150万円まで大きく開きがありました。
「まずは安く作って、後から必要に応じて機能を足せばいい」と考え、最安値の制作会社に発注。契約書には「ホームページ制作費 一式」とだけ書かれており、ページ数やSEO対策の有無、更新方法についての具体的な説明は受けませんでした。
制作は短期間で完了したものの、完成したサイトは無料テンプレートの色とロゴを変えただけ。自社の強みやサービス内容は簡単な文章だけで、写真もフリー素材ばかり。検索してもほとんど表示されず、公開から2か月経っても問い合わせはゼロでした。
さらに、キャンペーン情報の掲載やサービス内容の追加を依頼したところ、1ページ追加で3万円、バナー1枚で1万円の追加費用が発生。結果的に初期費用30万円のはずが、半年後には50万円近くに膨らみました。
※これは実在の企業や人物を特定するものではなく、過去に当社で対応したご相談をもとに構成した架空のストーリーです。
ホームページ制作の見積もりを比較すると、制作会社や担当者によって費用に大きな差が出ることがあります。その中で「とにかく安いところ」を選んでしまうと、下記のような落とし穴にはまりやすくなります。
- 安価での制作は工数を削るため、テンプレートデザインの流用が多く、自社の強みやブランドが反映されない
- 集客やSEO対策などの施策がほとんど含まれていない
- 契約後に必要な機能追加や修正対応で追加コストが発生し、結果的に割高になる
特に中小企業では、初期費用を抑えたい気持ちが強いため、安さを最優先にした判断が長期的な集客力や企業イメージ低下につながるケースが多いのです。
対策
1.総額だけでなく「費用の内訳」を確認する
見積書の内訳を細かく確認し、デザイン・開発・SEOなど、何にどの程度コストがかかっているのかを把握します。「一式」とだけ書かれている場合は要注意です。
2.成果物のクオリティと費用のバランスを比較する
単に安いか高いかではなく、投資に見合う価値(ROI)があるかどうかで判断します。制作実績や同業他社の事例も確認しましょう。
3.契約前に追加費用の条件を明確化する
機能追加や修正が発生した際の料金体系を事前に確認し、「最終的にいくらまでかかる可能性があるか」を把握しておくことが重要です。
ポイント
安さだけで選ぶと、後から「集客できない」「修正費用がかさむ」という二重の失敗につながります。費用は単なるコストではなく、自社の成長への投資と考え、長期的な視点で判断することが成功の鍵です。
事例2.「知人・格安フリーランス」への依頼でトラブルが多発
東京都内で小さなカフェを経営しているC社は、開業2年目に「そろそろホームページを持って集客を強化したい」と考えました。
制作費用はできるだけ抑えたいと考え、知人の紹介で格安フリーランスに依頼することにしました。見積もりは20万円と、制作会社に依頼する場合の半額以下でした。
契約書は交わさず、やり取りはメールとチャットのみ。打ち合わせも最初の1回だけで、あとはフリーランスに任せて進める形になりました。
制作が始まると、納期が何度も遅れ、予定していたキャンペーンにホームページが間に合わない事態に。さらに途中から連絡が取りづらくなり、修正依頼を出しても「追加費用がかかる」と言われるようになりました。
そして完成したサイトは最低限のデザインと情報しかなく、集客導線やSEO対策はまったく考慮されていませんでした。公開後、アクセスも問い合わせもまったく増えずに半年が経過。結局、C社は改めて制作会社に依頼することになり、結果的に当初の予算を大幅に超える費用がかかりました。
※これは実在の企業や人物を特定するものではなく、過去に当社で対応したご相談をもとに構成した架空のストーリーです。
コストを抑えるために、知人や格安フリーランスにホームページ制作を依頼するケースは少なくありません。
しかし、制作体制や契約内容が曖昧なため、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 納期が大幅に遅れる
- 制作途中で連絡が取れなくなる
- 修正や保守対応が有償・不可能になる
- デザインや集客設計の専門性が不足している
結果として、公開できないサイトや使えないサイトになり、最終的に制作会社へ作り直しを依頼することになり、二重のコストがかかることもあります。
対策
1.契約書と仕様書を必ず作成する
口頭やチャットのやりとりだけではなく、納期・費用・修正回数・対応範囲を明記した書面を交わします。
2.制作体制やサポートの有無を確認する
一人で対応する場合、病気やスケジュール都合で対応できないリスクを想定し、代替手段やバックアップ体制の有無を確認します。
3.集客やSEOの実績をチェックする
制作実績だけでなく、「制作後に成果を出した事例」を確認して依頼判断を行いましょう。
ポイント
コスト削減のために選んだ方法が、最終的に時間・費用・信頼の損失につながることがあります。信頼できる制作パートナーを選ぶことが、長期的な集客力と企業価値を守る近道です。
事例3.「デザイン重視」で集客できないサイトに
新サービスの立ち上げを機に、あるIT企業がホームページ制作を依頼しました。社長のこだわりは「とにかくオシャレなデザイン」。制作会社にも「見た目を重視してほしい」と強調し、集客やSEOの話はほとんどしないまま制作が進められました。
完成したサイトは、アニメーションや高解像度の写真を多用したスタイリッシュな仕上がり。社内からも「カッコいい!」と評判でした。ところが公開後、思わぬ問題が発覚します。
- 問い合わせフォームへの導線が分かりにくく、ユーザーが途中で離脱
- ページが重く、スマホ表示では特に読み込みが遅い
- SEO対策がされていなかったため、検索しても会社名以外ではヒットしない
結果、公開から3か月経っても新規問い合わせはほとんど増えず、集客にはつながりませんでした。
※これは実在の企業や人物を特定するものではなく、過去に当社で対応したご相談をもとに構成した架空のストーリーです。
見た目の美しさに惹かれ、デザイン性だけを重視してホームページ制作を進めると、集客や成果に結びつかないことがあります。
- ユーザー導線が複雑で問い合わせにたどり着けない
- SEO対策がされておらず検索流入が見込めない
- デザイン優先でページ表示速度が遅くなる
これでは、結果的に「オシャレだけど売れない・集客できない」サイトになってしまいます。
対策
1.デザインとマーケティングの両立を意識する
デザインは企業イメージやブランディングに重要ですが、ホームページ制作では問い合わせや購入につながる導線設計を同時に行う必要があります。
2.SEO対策を構築段階から組み込む
後からSEO対策を追加するのはコストと時間がかかるため、企画段階からキーワード設計や内部構造の最適化を進めます。
3.ページ速度やモバイル表示も重視する
ユーザー体験(UX)を損なわないよう、軽量化やモバイル最適化を実施します。
ポイント
デザインはあくまで手段であり、目的は集客や成果です。経営者視点では「見た目の良さ」と「ビジネス成果」の両立が欠かせません。
事例4.「運用・保守」を想定せず公開後にトラブル発生
地方で雑貨店を展開するE社は、新規顧客の獲得を目的にホームページを制作しました。制作会社に任せてサイト自体は問題なく公開できたものの、公開後の更新や保守について深く考えていなかったことが思わぬ落とし穴となりました。
新商品が入荷するたびにページの更新を依頼すると、1回の修正で数万円の追加費用が発生。更新頻度が高い業種だったため、数か月で予算を大幅に超える結果となりました。さらに、CMSやプラグインの更新が行われておらず、ある日サイトがエラー表示になり、問い合わせフォームが利用できなくなるトラブルも発生。復旧には追加費用と数日の時間が必要でした。
また、半年以上情報が更新されなかったことで、「このお店はもう営業していないのでは?」と顧客に誤解されることもあり、ブランドイメージにも悪影響を及ぼしました。
※これは実在の企業や人物を特定するものではなく、過去に当社で対応したご相談をもとに構成した架空のストーリーです。
ホームページは公開がゴールではなく、運用と改善が成果を左右します。しかし、制作段階でこの運用・保守を十分に想定していないと、公開後に下記のような問題が発生します。
- 更新作業のたびに高額な費用が発生
- CMSやプラグインの更新がされず、セキュリティリスクが高まる
- 情報が古くなり、ユーザーからの信頼を失う
こうした事態は、「公開後に誰がどのように管理するのか」という運用体制や予算計画を最初から組み込まないことが大きな原因です。
対策
1. 更新方法と頻度を明確化する
社内で更新するか、制作会社に依頼するかを決め、作業範囲と費用を契約時に明記します。
2. 保守・セキュリティ対応の契約を検討する
セキュリティ更新や障害対応を含めた保守契約を結ぶことで、長期的な安定運用が可能になります。
3. 公開後の改善計画を立てる
アクセス解析やSEO評価を元に、継続的な改善を行う仕組みを用意します。
ポイント
運用と保守を考慮しない制作は「短命サイト」になりがちです。長期的な費用対効果を考えるなら、公開後の体制構築まで含めて計画しましょう。
事例5.「丸投げ依頼」でイメージと全然違うサイトに
地方で建設業を営むF社は、新規顧客の獲得を目的に初めてホームページ制作を依頼しました。社内にITに詳しい担当者がいなかったため、経営者は「プロに任せれば安心だろう」と考え、制作会社にほぼ丸投げで依頼を進めました。
制作は順調に進んでいると思われましたが、完成したサイトを見て驚きました。
- ターゲットとしたかった地元の個人客ではなく、企業向けの内容になっている
- 自社の強みである「地域密着」「小回りの良さ」がほとんど表現されていない
- 制作会社の判断で進んだため、想定外のページ構成となり、修正依頼が多数発生
結果として納期は遅れ、追加修正費用も発生。公開後も問い合わせは伸びず、「自社の魅力を全く伝えられないサイトに時間とお金をかけてしまった」と後悔することになりました。
※これは実在の企業や人物を特定するものではなく、過去に当社で対応したご相談をもとに構成した架空のストーリーです。
「プロに任せれば大丈夫」と、制作会社に完全丸投げしてしまうと、完成したサイトが自社の意図やブランドと大きくかけ離れることがあります。
- ターゲット層や訴求ポイントがずれている
- 自社の強みが十分に反映されていない
- 制作側が想定した内容で進んでしまい、修正が多発
このような問題は、依頼側と制作側の間に目的・価値観・ゴールの共有不足があると起こりやすく、特に初めてホームページ制作を発注する企業では顕著です。
対策
1.要件定義をしっかり行う
目的・ターゲット・必要機能・デザインテイストなどを具体的に共有します。
2.制作過程での確認フローを作る
ワイヤーフレームやデザインカンプの段階でレビューを行い、ズレを早期に修正します。
3.担当者が定期的に進捗を把握する
任せきりではなく、経営者や担当者が責任を持って進行管理に関与することが重要です。
ポイント
丸投げは「楽」ですが、「成果の出ないサイト」を生む原因にもなります。制作は制作会社との共同プロジェクトであるという意識を持ちましょう。
「初めてのホームページ制作で失敗したくない…」
「制作会社としっかり相談しながらホームページ制作を進めたい!」
そんな方はぜひrelationへご相談ください。
豊富な制作実績とSEO・集客ノウハウを活かし、貴社の目的や予算に合わせた最適なプランをご提案します。
依頼前に絶対に確認すべき3つのチェックポイント
ホームページ制作で失敗しないためには、契約前に「見積書の中身」「契約範囲」「将来的な修正や機能追加の条件」の3点を必ず確認することが重要です。
これらを曖昧にしたまま依頼すると、費用や対応範囲で想定外のトラブルが発生し、余計なコストと時間を失うリスクが高まります。
1.見積書の内訳はここをチェック
内訳を見る際のポイントは、「一式」と書かれた項目の中身を必ず確認することです。
「ホームページ制作費 一式 ◯◯円」とだけ記載されている場合、具体的に何が含まれているのかが分からず、後から追加費用が発生するケースがあります。
確認すべき主な項目
- ページ数(トップページ+下層ページ数)
- デザイン費用(オリジナルかテンプレートか)
- コーディング費用(レスポンシブ対応の有無)
- CMS導入費用(WordPressなど)
- 写真・文章の作成費(素材提供か制作会社手配か)
- SEO対策や集客設計の有無
また、見積もり比較時は「総額」だけでなく「内訳ごとの単価」も確認しましょう。これにより、各制作会社がどこにコストをかけているかが分かり、適正価格の判断材料になります。
2.対応範囲と納品後のサポート
ホームページは公開して終わりではありません。
公開後に「画像差し替え」「文章修正」「ページ追加」などの作業が必要になることは少なくありませんが、契約範囲に含まれていない場合は別料金になることがあります。
確認すべき主な項目
- 修正対応の範囲と回数(デザイン確定後は別料金になる場合あり)
- 公開直後の軽微な修正が無償か有償か
- 納品後のサポート内容(操作説明・マニュアルの有無)
- 障害発生時やサーバートラブル時の対応可否と費用
さらに、SEOや集客に関するサポートが含まれるかも要確認です。制作会社によっては、納品後のアクセス改善やキーワード調整は別契約になる場合が多くあります。
3.将来的な修正・機能追加の対応と費用感
制作時に必要な機能だけで判断すると、将来的な運用で大きな誤算が生まれます。
例えば、事業拡大に伴うページ追加や、予約システム・EC機能などの拡張を後から行う場合、初期設計によっては大幅な改修が必要になることがあります。
確認すべき主な項目
- CMS導入の有無と編集可能範囲(テキスト・画像・ページ構造)
- 機能追加や仕様変更が発生した場合の作業単価
- 他社や社内で修正可能な構造になっているか
- 長期的な保守・管理プランの有無と料金
経営者視点では、初期費用だけでなく5年先までの総コストを見据えて判断することが、失敗を防ぐ最大のポイントです。
ホームページ制作費用の相場と見積もりの考え方
ホームページ制作の費用は、サイトの目的や機能、制作会社の規模によって大きく変わります。ここでは、ざっくりとした相場感と、見積もり金額の考え方を簡単に整理します。
より詳しい価格表やケース別費用については、別記事で解説していますので、そちらも参考にしてください。
制作費の目安
ホームページの制作費の目安は、サイトの種類や規模によって異なります。ここでは代表的なものの目安をご紹介します。
名刺代わりの小規模ホームページ
テンプレート利用:10〜25万円
オリジナルデザイン:20〜40万円
集客目的のコーポレートサイト
テンプレート利用:50〜120万円
オリジナルデザイン:80〜200万円
独自仕様のEC機能や予約機能のあるホームページ
テンプレート利用:150〜250万円
オリジナルデザイン:200万円以上
※あくまで目安であり、ページ数・機能・デザイン品質によって変動します。
複数社の見積もりがバラバラな理由
同じ条件で見積もりを依頼しても、制作会社ごとに金額が異なるのは珍しくありません。主な理由は以下の通りです。
- 制作工程や関わるスタッフ数の違い(ディレクター、デザイナー、SEO担当など)
- デザインのクオリティや独自性(テンプレート利用かフルオリジナルか)
- SEO・集客設計の有無(初期設計に含まれているか後付けか)
- 納品後サポートや保守契約の有無
価格だけで判断せず、「何が含まれているか」を見極めることが重要です。
「安い・高い」ではなく“納得できる価格”を見極める
ホームページ制作は単なる費用ではなく、自社の成長への投資です。安いだけでは成果が出ない場合もあれば、高額でもROIが高いケースもあります。
見極めのポイントは、
- 費用の内訳と成果物のバランス
- 長期的な運用コストも含めた総額
- 制作会社の実績と集客効果の再現性
を総合的に判断することです。詳細な見積もり比較方法や判断基準については、相場記事にて解説しています。
ホームページ制作のより詳しい相場、価格がバラつく理由、制作費の内訳については別記事にてご紹介していますので、そちらも併せてぜひご覧ください。
まとめ|ホームページ制作で失敗しないために
ホームページ制作は、自社の集客やブランド価値を高めるための重要な投資です。
しかし、安さだけで制作会社を選んだり、契約内容や対応範囲を曖昧にしたまま進めたりすると、成果が出ない・追加費用がかさむといった失敗につながります。
今回ご紹介した5つの事例から分かるように、失敗を防ぐためには以下が重要です。
- 見積書の内訳や契約範囲を明確にする
- デザインと集客のバランスを意識する
- 運用・保守・将来的な拡張まで見据える
ホームページ制作は単なるコストではなく、長期的な成果を生むための経営戦略の一部です。短期的な金額の安さよりも、投資対効果(ROI)や継続的な集客力を重視して判断することが成功の鍵となります。
「初めてのホームページ制作で失敗したくない」
「制作会社としっかり相談しながら進めたい」
そんな方は、ぜひrelationへご相談ください!
豊富な制作実績とSEO・集客のノウハウをもとに、貴社の目的や予算に合わせた最適なご提案をいたします。