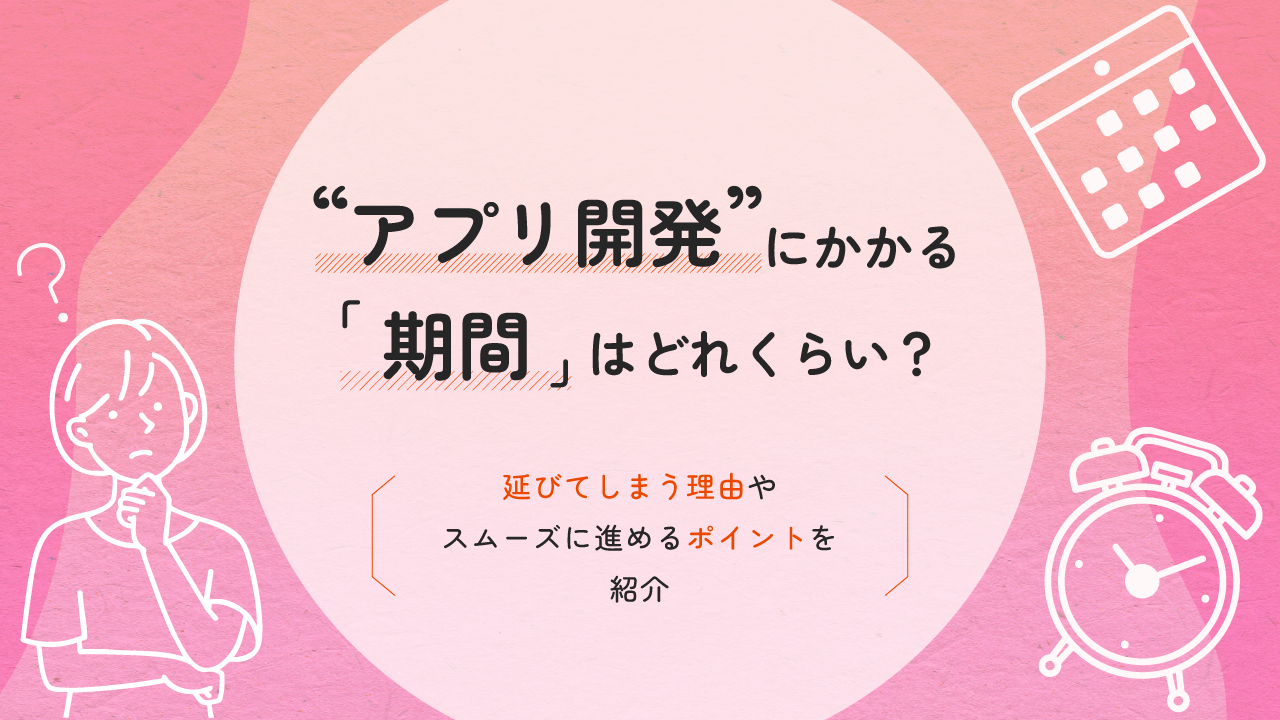アプリ開発を検討するうえで、「どれくらいの期間がかかるのだろう」「期間が延びてしまったらどうしよう」といった懸念を抱えている方は少なくないでしょう。
アプリ開発の期間は、アプリの種類や規模、開発手法などによって大きく変わります。また、事前準備の不足や、開発途中のトラブルによって、期間が延びてしまうことも珍しくありません。
本記事では、アプリ開発の期間の目安や、開発期間が延びてしまう原因、スムーズに開発を進めるためのポイントなどについて、詳しく解説します。
目次
アプリ開発の期間の目安
アプリ開発に要する期間の目安は、一般的に4~6ヶ月と言われています。ただし、開発するアプリのジャンルや内容、開発に携わるスタッフの人数、技術レベルなど、様々な要素によって、アプリ開発にかかる期間は変動します。
検索ツールアプリやショッピングアプリなど、機能がシンプルで比較的簡単に作れるアプリならば、1~3ヶ月程度で開発可能です。 一方、多機能で複雑なアプリの場合は6ヶ月以上、長ければ1年以上かかることもあります。
【パターン別】アプリ開発の期間
ここでは、ジャンルの違い、開発形態の違い、手法の違いのパターンに分けて、アプリ開発の期間の目安を紹介していきます。
ジャンルの違いによる開発期間の目安
アプリ開発に必要な期間や工数は、アプリの機能や複雑さによって大きく変動します。
例えば、業務・管理系アプリや金融系アプリのように、複雑なビジネスロジックや高度なセキュリティを必要とするアプリならば6ヶ月以上、長ければ数年かかることもあります。
アプリのジャンルごとの開発期間の目安は以下のとおりです。
| アプリのジャンル | 開発期間 |
|---|---|
| SNS系アプリ | 6ヶ月~1年 |
| EC系アプリ | 3ヶ月~1年 |
| ゲームアプリ | 3ヶ月~1年 |
| 店舗系アプリ | 1ヶ月~1年 |
| 金融系アプリ | 6ヶ月から数年 |
| 業務・管理系アプリ | 3ヶ月から1年 |
| 学習系アプリ | 1ヶ月から6ヶ月 |
| 位置情報系アプリ | 3ヶ月から1年 |
| 通話・メッセージ系アプリ | 6ヶ月から1年 |
開発形態の違いによる開発期間の目安
アプリの開発形態によっても、開発期間の目安は異なります。ここでは、代表的な2つの開発形態における、開発期間の目安を見ていきましょう。
フルスクラッチ型
フルスクラッチ型とは、アプリの機能をゼロから開発する方法です。オーダーメイドでアプリを作るので、クライアントの細やかなこだわりにも対応できます。
ただし、雛形となるものがない状態からスタートするため、開発期間が長くなりがちで、半年以上かかることが一般的です。プロジェクト規模が大きい場合や、細部にまでこだわる場合は、より一層長期的な開発となるでしょう。
クラウド型
クラウド型は、あらかじめ開発が完了している部品や機能を組み合わせてアプリを作る方法です。既存の部品を組み合わせるだけでアプリが完成するので、開発期間が短く、長くても3ヶ月ほどでリリースできます。
フルスクラッチに比べて短期での開発が可能な一方、自由度は低く高度な機能を搭載することは難しいという特徴があります。また、開発するアプリの要件に合わせて、適切な開発形態を選ばなければなりません。
手法の違いによる開発期間の目安
アプリ開発の手法によっても、開発期間の目安は大きく変わってきます。ここでは、代表的な2つの開発手法における、開発期間の目安を紹介します。
ウォーターフォール開発
ウォーターフォール開発とは、要件定義→設計→開発→テストといったように、上流工程から順番に進めていく開発手法のことです。各工程ごとの開発期間の目安は以下の通りです。
| 工程 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 開発の目的や解決したい課題、必要な機能、仕様、スケジュールなどを決める | 2週間~1ヶ月 |
| 基本設計 | アプリの機能や性能・画面デザインなど、アプリの外部を設計していく | 2週間〜1ヶ月 |
| 詳細設計 | 機能や動作・プログラム連携など、アプリの内部を設計する | 2週間〜1ヶ月 |
| 開発 | 設計図をもとに、プログラミング・コーディングを行うまた、アプリを動作させるためのサーバーやデータベースの構築も行う | 1ヶ月~2ヶ月 |
| テスト | アプリが設計通りにきちんと動くかを確認する | 2週間 |
| リリース | 完成したアプリをユーザーに公開するApp StoreやGoogle Playストアで公開する場合は審査が必要で、申請から結果が出るまでに時間を要する | 1週間 |
各工程がスムーズに進めば、半年程度が開発期間の目安となります。
ウォータフォール開発は、事前に細かい部分まで決めてから開発に取り掛かるので、開発期間を想定しやすく、予算も見積もりやすいのがメリットです。
ただし、アプリが完成してはじめてテストを行うため、もしテスト段階で不具合が見つかった場合は後戻りが生じ、開発期間が大幅に延びる可能性があります。
アジャイル開発
アジャイル開発とは、機能単位かつ短期間で、開発とテストを繰り返しながら進める手法です。開発期間は2~3ヶ月程度が目安となります。
機能の追加や仕様の変更を前提として開発を進めるため、要件定義や設計に時間をかけずに、短期間で開発を完了できるのが特徴です。開発の途中で不備が見つかった場合やクライアントから新たな要望が出た場合でも、工程内で柔軟に見直しを行えます。
一方で、開発の途中で何度も見直しを繰り返すため、工期が延びる可能性が高い点には注意が必要です。予定通りに開発を進めるためには、事前の十分な準備と関係者間の密なコミュニケーションが欠かせません。
アプリの開発期間が延びてしまう要因
アプリの開発期間が当初の予定よりも大幅に延びてしまうことは珍しくありません。ここからは、開発期間が延びてしまう主な要因を2つ紹介します。
事前の準備が不足している
アプリの開発期間が延びる要因の一つに、事前準備が足りていないことが挙げられます。
例えば、クライアント側でアプリの具体的なイメージができていないため、要件定義の段階で時間を要してしまうケースが挙げられます。要件定義はアプリ開発の大枠を決める大切なプロセスですが、ここで遅れが生じてしまうと、全体の工程全体が大きく遅れかねません。
また、開発側の見積もりが甘く、開発するアプリに対して人員やキャパシティが足りていないことで、工期が延びてしまうこともあります。
開発途中でトラブルが発生する
十分な準備をしてアプリ開発をスタートしたとしても、開発途中で予期せぬトラブルが発生し、工期が延びることもあります。よくあるトラブルとしては以下が挙げられます。
- アプリの審査が長引く
- テスト段階でバグが発生する
- 機能・仕様の変更が必要となり、追加工数が生じた
特に、審査に通らなかった場合には、審査落ちした理由を特定したうえで開発し直す必要があるため、いっそう期間が延びてしまいます。
アプリの開発期間を予定通りに進めるポイント
続いて、アプリの開発期間を予定通りに進めるためのポイントをいくつか見ていきましょう。開発側とクライアント側の双方に触れているため、計画的に開発を進めるうえでのヒントとして、ご活用下さい。
要件定義の精度を高める
アプリの開発期間を予定通りに進めるポイントの一つは、要件定義の精度を高めることです。
クライアントの要望が曖昧だと、それを明確にするだけで時間がかかってしまいます。
また、開発側がクライアントのニーズを細かにヒアリングできず、正確にくみ取り切れなかった場合も、開発が進むなかでの機能追加や仕様変更が生じ、工期の遅延を招きます。
要件定義の精度を高めるために、クライアント側は開発したいアプリのおおまかなイメージだけでなく、搭載したい機能や性能、デザインまで、できる限り具体的にしておくことが大切です。
一方、開発側は、クライアント側だけでアプリのイメージを言語化するのは困難であると理解しておきましょう。アプリによって達成したい目的や解決したい課題などのバックグラウンドから丁寧にヒアリングし、認識をすり合わせていくことが求められます。
ヒアリングの際には、言葉だけでなく図やイラストを用いながら情報を共有するのがおすすめです。そうすることで、認識の齟齬を防ぎ、より高精度な要件定義につながります。
開発期間には余裕を持たせる
予定通りにアプリ開発を進めるためには、開発期間に余裕を持たせることも重要です。
スケジュールを過密にしてしまうと、開発が間に合わず、完成に至らない可能性が高まります。また、短い期間内で無理に完成させたとしても、品質や効率に悪影響が出るおそれがあります。
修正が発生する可能性も考慮し、開発側とクライアント側で相談したうえで、余裕を持った開発期間を設定するべきです。
積極的にコミュニケーションをとる
アプリ開発をスムーズに進めるためには、関係者間での綿密なコミュニケーションが大切です。開発側のチームメンバー同士での積極的な情報共有はもちろん、開発側・クライアント間でも密に連絡を取り合うのが望ましいでしょう。
チーム内でのこまめな進捗報告や、クライアント側と開発側での定例会など、密なコミュニケーションを取っていくことで、認識のずれを防ぎ、機能や仕様の追加・修正による後戻りを回避できます。また、仮に問題が発生した場合にも早期発見できるため、大幅に遅れる事態を避けることが可能です。
また、クライアント側に進捗状況が伝わることで、双方の不安解消にもつながるでしょう。
最適な開発方法を選ぶ
先の見出しで挙げたように、開発手法・開発形態によって期間は異なります。
ゼロから開発を行うフルスクラッチ型の場合、自由度が高いものの、開発期間は半年以上かかることが一般的です。一方でクラウド型の場合、自由度は低いものの、比較的短期間での開発が可能です。
ウォーターフォール開発は、全体がスムーズに進めば、半年程度が開発期間の目安となるでしょう。アジャイル開発の場合、より短期間での開発も可能ですが、開発中の仕様変更は発生することが前提であるため、正確な開発期間が読みにくく、長期化する可能性もあります。
開発側は、クライアントの希望を汲み取ったうえで、開発手法・開発形態との相性を判断し、適切な組み合わせで提案することが求められます。また、クライアント側も開発側に丸投げするのではなく、各手法、開発形態の特徴を理解しておくと良いでしょう。
お互いに同じイメージを持つことで、開発方法の選択に要する時間を短縮できます。 さらに、開発途中での予期せぬトラブルの発生防止にもつながり、予定通りの開発プロセスの進行が可能です。
信頼できる業者に依頼する
クライアント側が開発会社を選ぶ際には、事前に実績を確認したうえで検討することが大切です。 実績が豊富な開発業者に依頼すれば、スムーズな進行と、高品質な成果物を期待できるでしょう。そのような会社であれば、人員や技術、キャパシティの不足から、工期が延びる心配も少ないです。
開発会社のホームページの事例や実績、口コミやレビューなどをチェックし、会社の評判やスキルの高さ、自社が開発したいアプリとの相性などを見極めたうえで、依頼先を選びましょう。
まとめ
本記事では、アプリ開発の期間の目安や、開発期間が延びてしまう要因、予定通りに進めるためのポイントなどについて、詳しく解説しました。
アプリ開発の期間は、開発するアプリのジャンルや、開発形態、開発手法などによって大きく異なります。 また、事前の準備不足や開発途中のトラブルが原因で、開発期間が大幅に延びてしまうこともあります。
アプリ開発を予定通りに進めるためには、要件定義の精度を高めたり、余裕を持ってスケジュールを立てたりと、できる限りの対策を打つ必要があります。 さらに、関係者間で積極的にコミュニケーションをとることで、認識のずれを防ぎ、トラブルの早期発見・早期対応につなげることが重要です。
アプリ開発のスムーズな進行を目指すなら、ぜひ株式会社relationにご相談ください。
豊富な開発実績を持つ経験豊富なエンジニアが在籍しており、プロジェクトの特性に合わせた最適な開発手法をご提案いたします。