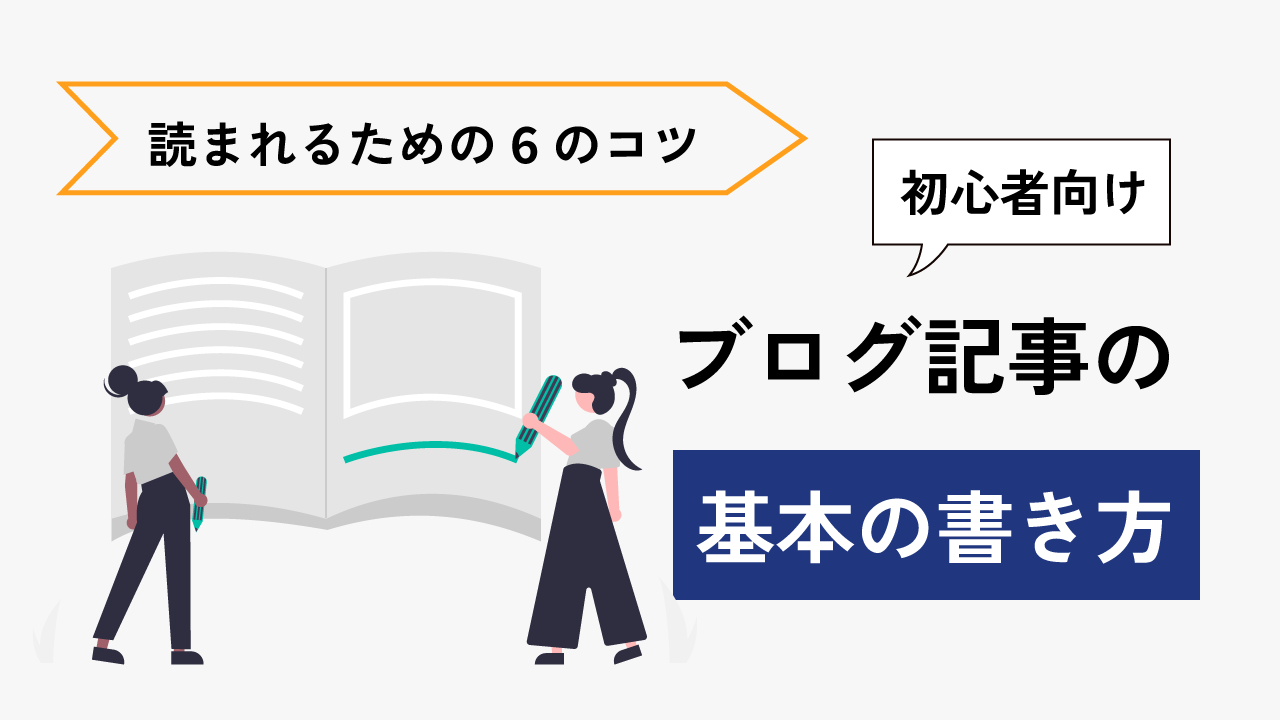はじめに
こんにちは!株式会社relationの解析・マーケティング施策担当、みえこです。
Webディレクターとして案件を推進するうえで、コンテンツやLP、広告施策の軸がブレていると感じたことはありませんか?
その原因の多くは、「ペルソナ設計」の欠如または設計精度の低さにあります。
本記事では、上級ウェブ解析士として日々Web施策に向き合う中で培った経験をもとに、ペルソナ設計の基礎から活用法までを、実践目線でわかりやすくご紹介します。
この記事はこんな方におすすめです!
- 「なんとなく」で決めたターゲット像に不安がある
- コンバージョン率が頭打ちで、「本当にこのターゲットでいいのか?」と疑問を抱えている。
- ペルソナ設計の正しいやり方を体系的に理解したい
ペルソナ設計とは?
Web施策においてよく出てくる「ペルソナ設計」という言葉。なんとなく聞いたことはあっても、実際に自分でゼロから設計するとなると、「これで合ってるのかな?」と手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、まず「ペルソナ設計とは何か?」という基本から、そのメリット、よく混同される“ターゲット”との違いまで、順を追って解説します。
ペルソナ設計とは?その目的と重要性
ペルソナ設計とは、サービスやプロダクトを届けたい“理想的なユーザー像”を、ひとりの具体的な人物像として詳細に描き出すことを指します。
ペルソナ設計では、年齢や性別、職業、ライフスタイル、価値観、日常の行動パターン、悩みや課題をできるだけリアルに設定し、まるで実在するかのような人物像をつくるのがポイントです。
こうして具体化されたペルソナは、誰に向けてどんな価値を届けるべきかという、マーケティングや制作の“軸”を明確にしてくれます。
「”なんとなくのターゲット像”で施策を進めた結果、訴求がブレて成果が出ない。」そうした問題を防ぐためにも、ペルソナ設計は非常に重要なステップなのです。
30代後半のWebディレクター、東京都在住、チームマネジメント経験あり。最近リニューアル案件のディレクションを任されたばかりで、訴求設計に悩んでいる
このように描くことで、その人物が抱える課題や思考の流れを想像しながら、施策ごとの判断や優先順位を決められるようになります。
ペルソナ設計のメリット
ペルソナをしっかり設計することで、さまざまな面で「軸」が生まれます。主なメリットは以下の通りです。
1. 訴求のブレをなくせる
「誰に、何を、どのように伝えるか」が明確になるので、コンテンツやLP、広告のコピーに一貫性が出ます。
伝えるべき相手が明確になることで、反応を引き出せる“刺さる訴求”を狙いやすくなり、成果にも直結しやすくなります。
2. チーム内の認識を統一できる
関係者間で「この人に届けたいんだな」と共通認識が持てるため、デザイン・開発・マーケティングなど、各部門での共有・意思決定もスムーズになります。
3. 施策の根拠として活用できる
上司やクライアントへの提案時、「この施策はこのペルソナのこの課題を解決するためです」と説明できれば、納得感が格段に高まります。
ペルソナとターゲットの違い
よくある誤解の一つが、「ペルソナ=ターゲットのこと」と考えてしまうこと。
確かに似ている部分もありますが、両者には明確な違いがあります。
| ペルソナ | ターゲット | |
| 定義するもの | 具体的な1人のユーザー像(例:32歳、独身、都内在住のWebディレクター) | 想定される顧客層の属性(例:20〜30代女性) |
| 情報の細かさ | 詳細(生活背景・行動・悩み・価値観など) | 大まか(年齢・性別・職業など) |
| 主な目的 | 訴求軸の明確化・意思決定のブレ防止 | 市場のセグメント化 |
簡単に言うと、「ターゲット」は“集団”の輪郭を捉えるもので、「ペルソナ」は“その中の代表者1人を深掘りする”イメージです。
どちらがより重要かというより、ターゲットで大枠を把握し、ペルソナで戦略の具体化に落とし込むという使い分けが効果的です。
ペルソナ設計の具体的なステップ
ペルソナ設計は、「なんとなくユーザーっぽい人」を想像する作業ではなく、情報に基づいて具体的な人物像を“構築する”プロセスです。
ここでは、実務で活用できるように、4つのステップに分けて紹介します。
ステップ1:ペルソナ設計に必要な項目をまとめる
まず最初に行うべきは、「どんな情報を設計に含めるか?」の項目整理です。ここが曖昧なままだと、収集すべき情報もブレてしまいます。
最低限押さえておきたいのは、以下のような要素です。
- 基本属性:年齢、性別、職業、居住地、年収、学歴など
- 生活背景:家族構成、日常の行動パターン、趣味や価値観
- 業務・課題:業務上の役割、抱えている悩み、達成したいゴール
- 情報接触:よく使うデバイス、閲覧するメディア、SNS利用状況
- 購買・意思決定:サービスを知るきっかけ、意思決定の基準、よくある躊躇点
これらを「テンプレート化」しておくことで、メンバー間でも共通認識で進めやすくなります。
ステップ2:ユーザー情報の収集をする
次に、実際のユーザー像に近づけるための情報収集を行います。ここでは「定量」と「定性」両方の視点が重要です。
定量データの例
- Google AnalyticsやClarity、Search Consoleなどのアクセス解析
- 会員登録情報、アンケート結果、CVデータ
- ソーシャルメディアや検索ボリュームの傾向
定性データの例
- 顧客インタビュー、営業・CSチームからのヒアリング
- ユーザーの口コミ・レビュー・SNS投稿の読み解き
- カスタマージャーニーや過去の失注理由
現場に近い視点から拾うことが、リアルな人物像の輪郭を描くヒントになります。
もしデータが十分に揃っていない場合は、仮説ベースで作っても構いません(ただしその場合は、あとで必ず検証できるようにしておくことが大切です)。
ステップ3:1人の「人物像」に統合してストーリーを作る
ここがペルソナ設計の“山場”とも言えるステップです。集めた情報をもとに、「1人のリアルな人物として想像できるレベル」にまで落とし込みます。
単なるプロフィールの羅列ではなく、その人の行動や感情が見えるように、ストーリー性を持たせることがポイントです。
例:
「東京都在住のWebディレクター、37歳、2児の母。リモート中心の勤務で、子育てと仕事のバランスを重視。最近、大型案件のLPリニューアルを任され、コンバージョンが伸び悩んでいる原因を“ターゲットとのズレ”だと感じている」
このように描くことで、チーム内で「この人にとって何が価値か?」を議論しやすくなります。
ステップ4:情報をまとめ、チームで共有し、施策へ反映する
完成したペルソナは、ドキュメントやスライドにまとめて終わりではありません。
チームで共有し、「判断基準」として実務に活用することがペルソナ設計のゴールです。
活用の際は、以下のような場面で「そのペルソナだったらどう感じるか?」を判断軸にすると効果的です。
- LPのキャッチコピーやCTAの検討
- コンテンツ企画やキーワード選定
- 広告バナーや動画クリエイティブのトンマナ設計
- サービスの導線やUI改善案の評価
特に複数名でプロジェクトを進める場合、意思決定の共通言語としてペルソナがあると、主観によるブレを防げるのも大きな利点です。
ここまで具体的なステップを述べてきましたが、ペルソナ設計は「やってみると意外と難しい…」と感じるポイントも多く、つまずいてしまう方も少なくありません。
「いろいろ調べてはいるけど、ペルソナ設計がやっぱりよくわからない」
「データはあるけど、ストーリーに組み立てるところで手こずっている」
「チーム内でうまく共有できず、施策に活かせていない」
そんなときは、ぜひ一度、relationにご相談ください!
上級ウェブ解析士をはじめとするマーケティングチームが、ペルソナ設計から施策への落とし込みまで、一貫してサポートいたします。
成果につなげる!目的別ペルソナ設計活用例
ペルソナ設計は、「ただ作って終わり」では意味がありません。
重要なのは、実際の施策にどう活かすか。目的やフェーズごとに活用方法を変えることで、成果へのインパクトが大きく変わってきます。
ここでは、よくある3つのシーン別に、ペルソナ活用の具体例を紹介します。
広告・LP改善向けペルソナ活用例
<よくある課題>
- LPの離脱率が高い
- 広告コピーがクリックされない
- 訴求ポイントが毎回ブレる
<活用のアプローチ>
ペルソナが明確であれば、「この人はどんな課題を抱えていて、どんな言葉に反応するのか?」という視点でコピーや構成を組み立てることができます。
たとえば、30代の女性Webディレクターが「時間が足りず、チームマネジメントにも追われている」という人物なら、
×「誰でも簡単にできるマーケ施策」
○「現場を回しながら成果も出せる!時間のないディレクター向けマーケ支援」
のように、文言をチューニングすることでCTRやCVRが改善されるケースは多々あります。
SEO・コンテンツ設計向けペルソナ活用例
<よくある課題>
- 検索上位なのに、ページの滞在時間が短い
- 記事の構成がぼやけていて、誰に何を届けたいのか分からない
- キーワードは入っているのにCVにつながらない
<活用のアプローチ>
ペルソナを設計しておくことで、「検索した本人はどんな悩みを抱えていて、何を知りたいのか?」が明確になります。
たとえば、GA4導入のSEO記事でよくある失敗が、「GA4の特徴やUI変更点の説明から入ってしまい、読者の“今まさに困っていること”に応えていない」ケースです。
×「GA4(Googleアナリティクス4)は、Googleが提供する最新のアクセス解析ツールです」
○「“GA4って見方が分かりにくいし、設定が正しいのかも不安…”そんなあなたへ。この記事では〜」
ペルソナを「前任者からGA4を引き継いだけれど、設定の中身がよく分からず、“とりあえずレポートを出している”状態のWeb担当者」として設計しておけば、上記のようにより検索意図に刺さる見出し構成・導入文・CTAを作成しやすくなるのです。
コンテンツSEOについてはこちらの記事もご参考にどうぞ!
商品・サービス開発向けペルソナ活用例
<よくある課題>
- 新サービスのコンセプトが社内で定まらない
- 顧客ニーズがぼんやりしていて、何を優先開発すべきか迷っている
- ユーザー調査をしても施策に落とし込めていない
<活用のアプローチ>
ペルソナ設計をしておくことで、「実際のユーザーが、いつ・どこで・なぜ困るのか?」という課題起点でサービス設計ができるようになります。
たとえば、SaaS系ツールを検討中の企業向けに機能開発を検討する場合、
- ペルソナA:ITリテラシーが高く、機能より連携重視 → API周りを優先開発
- ペルソナB:非エンジニアで、UIの簡単さが重視 → 初期設定のUX改善を重視
このように「誰のための機能か?」が明確になることで、開発リソースの最適配分や、仮説検証精度が高まります。
以上のように、ペルソナ設計は広告、コンテンツ、開発など、あらゆるフェーズの“判断の基準”として活用できます。
「設計したまま活かせていない…」という方は、ぜひ一度、活用方法そのものを見直してみるのもおすすめです。
ペルソナ設計でよくある失敗とその対策
ここまで、ペルソナ設計の基本から活用例までを見てきました。
しかし、「ペルソナ設計まではできたが思ったように機能しない。」「設計したペルソナを活かしきれていない」と行き詰まっている方も多いのではないでしょうか?
この章では、実務の現場でよくある“つまずきポイント”とその対策について解説します。
失敗を未然に防ぎ、ペルソナを「成果につながる実戦ツール」として機能させるために、ぜひチェックしておきましょう。
失敗1.仮説だけで作ってしまい、実態とズレる
<よくある失敗パターン>
- チーム内の想像だけで人物像を作成してしまい、実際のユーザーと大きく乖離
- 顧客インタビューや数値データを参照せず、「こういう人だと思う」で進めてしまう
<対策>
ペルソナは「仮説」からスタートしてOKですが、必ず「検証」とセットで設計することが重要です。
できれば以下のようなデータを組み合わせて裏付けを取りましょう。
- アクセス解析(GA4・Clarityなど)による行動傾向
- 営業・CS・サポート部門からのユーザー声
- SNS・レビューなどのユーザー発信情報
- ターゲット層への簡易インタビュー
「机上の空論」ではなく、「現場の感覚」と「数値の裏付け」の両方を融合させるのが理想です。
失敗2.情報が詳細すぎて施策に活かせない
<よくある失敗パターン>
- 気合を入れすぎて、50項目以上のプロフィール情報を詰め込む
- “左利きで猫好き”など、施策に直接関係のない情報まで書き込んでしまう
- 結果、「で、これ何に使うの?」と言われてしまう
<対策>
ペルソナ設計における情報量は、「詳細さ」よりも「意思決定に役立つかどうか」が重要です。「その情報は施策の判断に使えるか?」という視点で取捨選択するクセをつけましょう。
また、以下のような構成で情報を整理すると、活用しやすくなります。
- 上部:基本属性(年齢・職業など)
- 中部:行動や課題、感情的背景(意思決定に直結)
- 下部:ストーリーや代表的な発言(コンテンツやコピーに活かせる)
「読む側が施策に使いやすい設計」を意識することで、チーム全体での活用率も向上します。
失敗3.設計後に活用されず、形骸化する
<よくある失敗パターン>
- 設計したペルソナを資料として提出して満足してしまう
- 定例会議や施策検討の場で、一度も参照されない
- 「あったけど誰も見てない」「更新されていない」状態で止まってしまう
<対策>
ペルソナは設計することが目的ではなく、施策の判断基準として使われて初めて価値が生まれます。
- ペルソナをスライド1枚に要約し、MTGや企画書に必ず添付する
- プロジェクトのキックオフ時や提案時に「この人に届ける」と明言する
- 定期的に「このペルソナは今も有効か?」と見直す運用を設ける
- CanvaやNotionなどで“見たくなる形式”にする
などの工夫を凝らし、活用される仕組みを用意することで、ペルソナは「形式的な資料」から「戦略の起点」へと生まれ変わるはずです!
ペルソナ設計は、正しく機能すればコンテンツ・広告・サービス開発など、あらゆる施策において戦略の土台となります。
一方で、仮説倒れや形骸化を招いてしまえば、ただの時間の浪費にもなりかねません。
小さく始めて、活用しながらブラッシュアップしていく。それが、実務における成功の近道です。
「設計はしたけど、これでいいのか不安」
「今のペルソナを見直したい」
そんなときは、ぜひ一度、relationにご相談ください!
上級ウェブ解析士をはじめとするマーケティングチームが、ペルソナ設計から施策への落とし込みまで、一貫してサポートいたします。
まとめ
ここまで、ペルソナ設計の基本から具体的なステップ、活用事例、そしてよくある失敗とその対策について解説してきました。
最後に、あらためて本記事のポイントを整理して、ペルソナ設計への第一歩を踏み出しましょう!
ペルソナ設計はマーケティングに必須
マーケティングの目的は、「価値を必要としている人に、適切な形で届けること」です。
その“必要としている人”を定義するのが、まさにペルソナ設計。
ペルソナがあることで、施策の方針に一貫性が生まれ、制作・運用・改善のすべてにおいて「なぜそれをやるのか」が明確になります。
広告、LP、コンテンツ、プロダクト開発など、どんな領域でもペルソナ設計はマーケティングの土台として機能します。
「誰のための施策か」を見失わないために
施策の実施に追い込まれ、数字を追っているうちに、つい見落とされがちなのが「この施策、誰のためのものだっけ?」という視点です。
この「見失い」こそが、訴求のズレや成果が出ない要因につながります。
そんな時こそ、一度立ち止まってペルソナ設計に立ち返ることが、的確な判断と成果への近道になります。
記事を読んだ今こそ、設計に取りかかるタイミング
ペルソナ設計は、「今まさにコンテンツを作っている」「施策を提案しようとしている」その瞬間が、一番の始めどきです。
ペルソナ設計について調べていてこの記事にたどり着いた今こそ、「誰のために施策を打つのか?」という問いに向き合うベストタイミング。
最初から完璧である必要はありません。仮説ベースでも、設計してみることで視野がクリアになり、次の一手が見えてきます。
「理論はわかったけど、実際ペルソナ設計するとなるとやっぱりよくわからない」
「どうすればうまく施策に活かせられるんだろう?」
そんなときは、ぜひ一度、relationにご相談ください!
上級ウェブ解析士をはじめとするマーケティングチームが、ペルソナ設計から施策への落とし込みまで、一貫してサポートいたします。