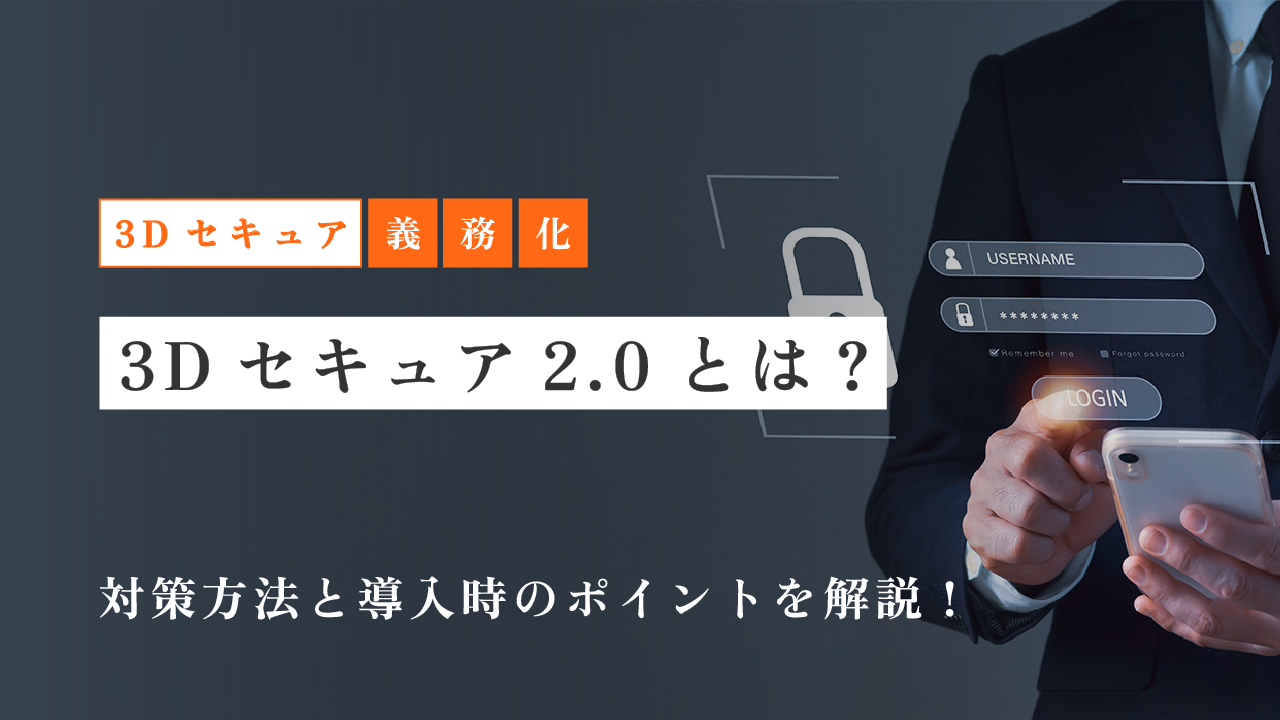こんにちは!relationのリコです。
近年、オンラインショッピングの利用拡大に伴い、クレジットカードの不正利用が増加しています。これに対応するため、決済セキュリティの強化がECサイト運営者にとって重要な課題です。
中でも鍵を握るのが「3Dセキュア」の導入。
経済産業省は2025年3月末までに3Dセキュア2.0(EMV 3-Dセキュア)の義務化を目指す方針を発表しました。
「3Dセキュアって聞いたことはあるけど、どんな仕組みなのか分からない…」
「義務化されるって聞いたけど、実際に何をすればいいの?」
そんな不安を抱えている方も多いかもしれません。
この記事では、3Dセキュアの基本知識、義務化の背景、導入メリット、そして具体的な手順を分かりやすく解説します。
セキュリティ対策を見直し、安心して利用されるサイト作りを進めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください!
目次
3Dセキュアとは?
3Dセキュア(EMV 3-D Secure)は、クレジットカード決済時に本人認証を行うことで、不正利用を防ぐ仕組みです。クレジットカード会社とEC事業者の間でデータをやり取りし、リスクベース認証(RBA)を活用することで、安全性と利便性を両立させています。
特に注目されているのが、従来の「3Dセキュア1.0」に代わり新たに導入された「3Dセキュア2.0」。
この新しいバージョンでは、ユーザー体験の向上が図られており、追加認証が必要な場合でも画面遷移を最小限に抑える設計がされています。
3Dセキュア1.0と2.0の違い
| 3Dセキュア1.0 | 3Dセキュア2.0 | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・パスワード認証 ・認証画面に遷移する | ・低リスクの取引では認証不要 ・最小限の画面遷移 |
| 認証方法 | ・パスワード入力 | ・ワンタイムパスワード ・生体認証(指紋認証・顔認証) ・デバイス認証 など |
| セキュリティ | 比較的低い ・フィッシング詐欺 ・パスワード漏洩 のリスク | 高い ・リスクベース認証の導入 |
| カゴ落ちリスク | 高い ・認証画面で離脱の可能性 ・パスワードを忘れると決済不可 | 低い ・スムーズに決済可能 ・高度なセキュリティによる安心感 |
3Dセキュア1.0は事前に設定した静的パスワードを使用する方式で、不正利用防止には一定の効果がありましたが、パスワード忘れや入力ミスで決済を完了できない場合もあり、ユーザーにとっては少々使い勝手が悪いものでした。
また決済途中で、認証画面への遷移が行われることにより「カゴ落ち」のリスクも高まるため、ECサイト運営者にとっても課題が多くありました。
一方、3Dセキュア2.0では認証方式が動的認証に進化し、ワンタイムパスコードや生体認証(指紋認証・顔認証)など、セキュリティの高度化が図られています。
また、カード会社との情報連携が強化され、デバイス情報や取引履歴を活用したリスクベース認証が導入されました。
これにより、低リスクな取引では追加認証が不要になり、よりスムーズに決済が進みます。
セキュリティと利便性の両方を向上させた仕組みと言えるでしょう。
3Dセキュア義務化の背景
義務化が求められる理由
オンライン決済の需要が急増する一方で、クレジットカードの不正利用も深刻化しています。
特に、ECサイトにおける「なりすまし」や「不正チャージバック」の被害が増加し、カード会社やEC事業者にとって大きな課題となっています。
こうした状況を受け、経済産業省は2025年3月末を目処に 「ECサイトでの本人認証(EMV 3-Dセキュア)」の導入を義務化すると発表しました。
決済時の本人確認を強化し、不正利用リスクを低減することが目的とされています。
規制のスケジュールと対象範囲
3Dセキュア義務化の対象となるのは、 クレジットカード決済を導入しているECサイト全般 です。特に、以下のようなサイト運営者は早急な対応が求められます。
- クレジットカード決済を主要な決済手段としているECサイト
- 高額商品の販売や定期購入サービスを提供している事業者
- 国際ブランド(Visa、Mastercard、JCBなど)のカード決済を導入している企業
義務化の正式な適用日は2025年3月末ですが、システムの実装やユーザー向けの対応準備を考えると、 今すぐ導入の検討を始めるべきです。
未対応のままでは、利用している決済代行サービスによっては制限がかかる可能性があるため、計画的な対応が必要です。
3Dセキュアを導入するメリット
3Dセキュアの導入は単に義務化への対応というだけでなく、ECサイト運営者と利用者の双方に大きなメリットがあります。
ECサイト運営側のメリット
1. チャージバック被害の軽減
不正利用が発生すると、カード会社からECサイト運営者に対し、売上の返金(チャージバック)を求められるケースがあります。
3Dセキュアを導入すれば、カード会社側が本人確認を行うため、EC事業者の負担が大きく減ります。特に高額商品の販売を行うサイトにとっては、大きなメリットといえるでしょう。
2. セキュリティ強化による信頼性向上
ユーザーにとっても、「安全なECサイトを選びたい」という意識は強いはず。3Dセキュアを導入することで、「安全な決済環境を提供しているサイト」として認識され、ユーザーからの信頼を得やすくなるのも大きなメリットです。
3. クレジットカード決済の継続利用促進
3Dセキュア非対応のECサイトでは、今後、一部のカードブランドで決済が制限される可能性があります。早期に対応しておくことで、クレジットカード決済をスムーズに継続し、販売機会の損失を防ぐことが可能です。
ユーザー側のメリット
1. クレジットカードの不正利用防止
3Dセキュアを導入することで、第三者による「なりすまし決済」を防ぐことができるようになります。万が一カード情報が漏洩しても、追加認証が必要なため、被害を最小限に抑えることができます。
2. より安心してECサイトを利用できる
3Dセキュアが導入されたサイトでは、「安全なサイトで買い物している」という安心感を持って決済ができます。
その結果、ECサイトの利用頻度が高まり、リピーターの増加にもつながるかもしれません。
3. 動的認証によるスムーズな決済
3Dセキュア2.0では、 生体認証やワンタイムパスコードなど、より便利な認証方式が導入 されています。
毎回パスワードを覚えておく必要がないため、スムーズに決済ができるようになりました。
3Dセキュア未対応のリスク
3Dセキュアの導入が義務化される中、対応を怠ることには大きなリスクが伴います。
1.チャージバック増加
クレジットカードの不正利用による「チャージバック(不正取引の返金要求)」のリスクが高まることは、3Dセキュア未対応の最も深刻なリスクの一つです。
不正利用が発生すると、カード会社からECサイト側に返金が求められ、売上が失われるだけでなく、手続きにかかるコストや時間的な負担も増大します。
また、チャージバックが一定の基準を超えると、カード会社や決済代行サービスからペナルティを受ける可能性も!
最悪の場合、カード決済の利用停止などの措置が取られることもあり、ECサイト運営に深刻な影響を及ぼします。
顧客離れ
3Dセキュアに対応していないサイトは、「安全性に不安がある」と判断され、ユーザーの信頼を失うリスクがあります。
特に、クレジットカード決済を多く利用するユーザーはセキュリティ意識が高く、決済時に3Dセキュアの認証画面が表示されないと、不安を感じるでしょう。
また、カード会社によっては3Dセキュア未対応のサイトでの取引をブロックするケースも増えており、決済が完了しないことが原因で、購入を諦めてしまうユーザーが出る可能性もあります。
3Dセキュア未対応のペナルティ
3Dセキュア導入が義務化されることより、対応しないECサイトには決済代行サービスからの取引制限や、カード会社からの制裁措置が科される可能性があります。
- 一部のクレジットカード決済が利用できなくなる
- 決済手数料の引き上げ
- 取引の審査が厳格化される
- 決済代行サービスの契約条件が変更される
クレジットカード決済は、ECサイトにとって重要な決済手段の一つ。
3Dセキュア未対応のまま運営を続けることは、「不正利用されやすいサイト」「信頼性の低いサイト」として評価される可能性があるため、ECサイトの存続や成長を考えると早めの対応が求められます。
今後のEC市場において 「安全な決済環境の提供」は、顧客獲得の必須条件!
義務化対応だけでなく、 ユーザーの信頼を得るためにも、早めの3Dセキュア導入を検討しましょう。
3Dセキュアの導入の流れ
導入前に必要な準備
まず、現在利用している決済代行サービスが3Dセキュア2.0に対応しているかを確認します。対応していない場合は、別のサービスへの切り替えを検討する必要があります。
またECサイトのシステムが3Dセキュアの認証フローに対応できるかも重要。
特に、カートシステムや決済ページの改修が必要な場合は、開発スケジュールを早めに調整しておくことが求められます。
他にも3Dセキュア導入後の決済フローをシミュレーションし、利便性を損なわない設計にすることも大切です。
サービス選びのポイント
決済代行サービスやカード会社ごとに、3Dセキュアの導入方法や仕様が異なります。
- 最新の3Dセキュア2.0に対応しているか
- 追加費用の有無(導入や運用コスト)
- 認証方式の種類(生体認証、ワンタイムパスコード対応の有無)
- ECサイトへの実装方法(API連携やプラグインの有無)
導入後の運用も考慮し、サポート体制が整っているプロバイダーを選ぶことが大切です。トラブル発生時に迅速な対応が可能かどうかも、重要な判断基準となります。
導入のポイント
3Dセキュアを導入した後は、 実際に決済がスムーズに行えるかテストを実施しましょう。特に、以下の点を重点的にチェックします。
- 認証プロセスが正常に動作するか
- スマートフォンやPCなど、異なるデバイスでも問題なく決済できるか
- ユーザーが迷わず操作できるか
また、 顧客への周知も忘れずに行うことが重要です。
認証画面の変化に戸惑う利用者が出ないように、事前にFAQやヘルプページを整備するとスムーズでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
オンライン決済のセキュリティ強化が求められる中、3Dセキュアの導入はECサイト運営者にとって必須の対応です。
特に、2025年3月末には義務化が予定されており、未対応のままでは チャージバックの増加や決済制限といったリスク を抱えることになります。
早めの対応で、不正利用リスクを軽減し、スムーズに移行しましょう!
とはいえ、『何から始めればいいのか分からない』『自社のシステムで対応できるのか不安…』と感じている方も多いかもしれません。
株式会社relationでは、ECサイトの構築から運営までトータルでサポートしています。
当社の強みは以下の点です:
✅ システムとデザインの両立
エンジニアとデザイナーが社内で連携し、機能性とデザイン性を兼ね備えたECサイトを構築。
✅ SEO・マーケティング支援
リリース後も継続的なSEO対策と広告運用で、長期的な売上拡大をサポート。
✅ 運営サポートの充実
フォトグラファーによる物撮り、多言語対応、決済システムの最適化など、運営をスムーズに進める体制を提供。
3Dセキュア対応のECサイト構築を検討中の方は、ぜひこちらのページをご覧ください。